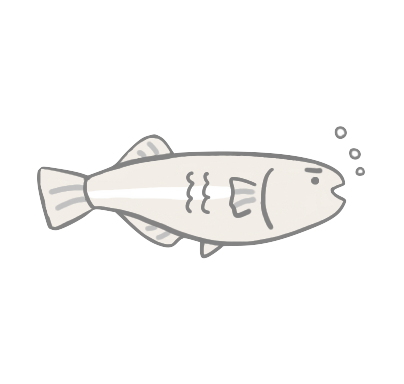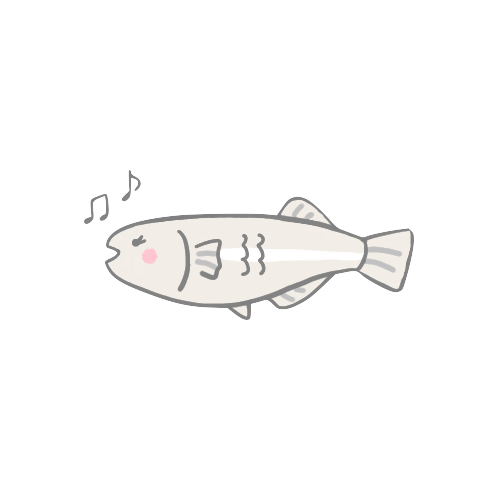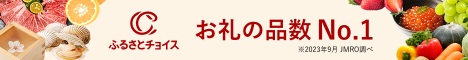資産運用はしてみたいけど、大事なお金が減るのも怖いしやっぱり難しそう・・!
初めて投資を始めるには足踏みしてしまうな・・ってことありますよね。
そのような状況の中でも、ふるさと納税は投資をするよりも断然リスクが少なく、
おトクを享受できる制度です。
今回は初めての方向けに、そんなおトクな【ふるさと納税】の仕組みと
自分の限度額はいくらなのか、かんたんシミュレーションを使って確認したいと思います。
ふるさと納税とは


仕組みとメリット
「ふるさと納税」とは、あなたが応援したいと思う自治体に寄付ができる仕組みです。
寄付をすることで、地域貢献につながるだけではなく、地域の特産品・名産品がお礼の品として貰えるため、今では多くの方に利用されています。
さらに、寄付をした金額は税金から控除・還付されるため、自己負担が軽減されます。
私たちが支払う所得税・住民税の計算は①収入から②支出を差し引いた残りの金額に
それぞれ税率をかけて計算されます。
- 収入(個人事業主の売上・サラリーマンのお給料等)
- 支出(個人事業主の経費・サラリーマンの給与所得控除額)と所得控除(基礎控除・扶養控除・保険料控除等)
ふるさと納税をすると、この税金の計算をする上で差し引く②の所得控除が増える為
結果的に税金の負担が減るのです。
分かりやすく、シンプルな図表で確認しましょう。


ふるさと納税をしない場合
グラフにサンプルの数字を入れました。
このケースで、ふるさと納税をしない場合の所得税・住民税の合計は「20」です。


ふるさと納税をする場合
同じケースで、ふるさと納税で「10」寄付をすると、
その分が寄付金控除として税金の計算上控除されるため所得税・住民税が少なくなります!
下記の図のように、所得税・住民税の額が「20」→「10」に減りました!


所得税・住民税の額「10」+ふるさと納税「10」の合計「20」は、
ふるさと納税をしない場合の所得税・住民税の合計は「20」と同じ金額になります。
いくら位おトク?の具体例
いったいどれ位おトクなのでしょう?実際の数字に当てはめてみてみましょう。
【寄付金控除限度額50,000円の人が限度額まで寄付した場合】
| 家計から見た場合 | memo | |
| ①ふるさと納税(寄付) | △50,000円 | 先に現金の支出が発生する |
| ②返礼品の受取 | +15,000円 | 返礼品は寄付額の3割で計算 |
| ③所得税・住民税の減額 | +48,000円 | 2,000円を超える部分が寄付金控除の対象なので、50,000円△2,000円です。 |
| 差引 | +13,000円 | おトク♪おトク♪ |
多くの自治体で寄付額の3割程度の返礼品を頂ける為、ふるさと納税という寄付をすると
自己負担2,000円で様々な返礼品がもらえる!
という仕組みになっています。
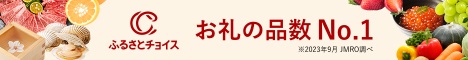
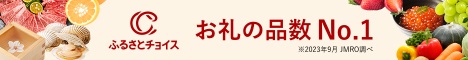
このような指定がされるまでは、返礼割合5割は当たり前・・
のような各自治体での加熱競争が起きていました。
ふるさと納税する側としては、正直とっても有難かったですね。
ただメダカ家がふるさと納税を始めた2014年(平成26年)は、
ふるさと納税の限度額も少なく、翌2015年(平成27年)に上限額が倍になりました。
そうしたことを考えてみると、返礼品割合が3割に制限されたとしても
プラスマイナス・・まだまだプラス!です♪
被災地支援・社会貢献がしやすくなるというメリット


また個人的には、災害大国である日本において、被災地支援がしやすくなる
という点が大きなメリットだと感じています。
災害が発生すると、様々なふるさと納税のポータルサイトでも
被災地への寄付が募られます。当然に、被災地へ寄付をしても返礼品はありません。
それでも、現金で被災地へ寄付をするゆとりがなくても、
ふるさと納税制度を利用して、控除限度額の中で寄付をすることが出来れば、
被災地支援がしやすくなる方は多いのではないでしょうか。
メダカ家も、被災地への寄付はふるさと納税制度を利用して
1地域1万円を繰り返してきました。
災害が起こらないことが1番ですが、もし起こってしまったときは
この制度を利用して、被災地への支援を続けていきたいです。
その他のメリット
そのほかにも
クレジットカード払いでポイントやマイルがたまる。
など、細かいメリットもありますね♪
デメリット
やはり何ごとも、メリットがあればデメリットがありますが
メダカが感じる大きなデメリットを3つ挙げます。
- 本来納めるはずだった居住地の住民税が、寄付先へ移る
- 控除を受けるために、先に寄付(=支出)する資金が必要
- 必ずなにかしらの「手続き」が必要
ふるさと納税をすることにより減額される税金は所得税と住民税です。
国税である所得税は、納税先が日本という「国」であり
日本国内どこに住んでいても納税先は変わりません。
ところが、地方税である住民税はについては話が違います。
ふるさと納税がなければ、本来、居住地の住民税として納税される金額が
寄付先の地方自治体に流れる、という図式になっており
流出が多い地方自治体にとっては大きな問題となっています。
自身の地方自治体に寄付を集めたい為に、返礼品競争も過熱していったわけですね。
注意点
ふるさと納税の返礼品は一時所得の対象です!
ふるさと納税の返礼品で頂いた品の合計額が50万円を超える場合、
その超えた部分は一時所得の対象となり、税金が発生します。
返礼品が50万円を超えるには、166万円を超えるふるさと納税が必要なため
サラリーマンの場合、ざっくりと年収4,000万円クラスの方が該当します。
気を付けなくてはいけないのは、その年に他の一時所得がある場合です。
他の一時所得と合算して50万円を超える場合、
課税されますのでご注意を!
該当しそうな場合、詳しくは、国税庁HP、税理士、税務署にご確認下さいね♪
メダカ家のふるさと納税
メダカ家では2014年(平成26年)からふるさと納税を始めて7年目、
ふるさと納税の利用者がググっと伸びる前からの参入ですが
ふるさと納税の制度自体は2008年(平成20年)から始まっていますので
なぜもっと早く始めなかったか・・!と後悔したことを覚えてます。


しかし今でもなお、ふるさと納税の利用者は2割弱と聞いて驚きます。
まだふるさと納税をしたことが無い方も、今年こそは是非!ふるさと納税を始めましょう。
では、自分はいくらまでおトクにふるさと納税が出来るのか?が気になるところ。
税金を減らすことが出来る制度なので、税金を納付している=収入がある
場合に恩恵を受けられる制度です。
自分の収入に当てはめて、限度額を計算してみましょう。
かんたんシミュレーションで計算してみる


自分の収入だと自己負担2,000円でいくらまでおトクにふるさと納税できるの?
1番気にかかると思います。簡単な目安表はこちらです。
(ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」HPより)


それぞれの状況によって異なるので、少し詳しく
実際の控除限度額シミュレーションの使って見てみましょう。
ふるさと納税をする為のサイトが沢山あり、どこでも同じような計算が出来ます。
今回は、私が6年前から利用している
ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」にあるシミュレーションをつかってみましょう。
1.ふるさとチョイスのHPへ
ブルーのラインで囲った控除金額シミュレーションをクリック👇


2.かんたんシミュレーション
今回は、かんたんシミュレーションで計算します。
ブルーで囲ったかんたんシミュレーションをクリック👇


3.家族構成を選ぶ
プルダウンした中の選択肢から、自分の家族構成を選びます👇


4.年収を選ぶ
プルダウンした選択肢の中から、自分の年収を選びます👇


「もっとも近いもののお選びください。」と書いてありますが
迷ったら、少ない方を選択しておけば
控除額をオーバーすることがないので安心です。
5.寄付額(目安)を確認する
以上で入力が完了すると、すぐに寄付額(目安)が計算されます👇
メチャクチャ簡単ですね!!


たとえば年収750万円の方だったら、年収700万円と800万円で2回計算して
だいたいその平均額くらいだな・・という目安がつきますよ♪
6.注意事項
かんたんシミュレーションは、「かんたん」とつくようにシンプルな計算です。
医療費控除や住宅ローン控除など、所得控除がある場合は
詳細シミュレーションで計算することがおススメです。
まとめ


制度を理解して、自分で決めよう!
- 制度の意図を理解して、制度を利用する、利用しないを決めよう
- 寄付金控除限度額の目安は、自分で確認しよう
メリット、デメリットに記載したことがらから、賛成意見・反対意見のある制度です。
メダカは仕事で数多くの方の確定申告を担当していましたが、
自分の居住する地方自治体から税金を流出させる制度に賛同出来ない。という
確固としたポリシーでふるさと納税はしない、という方が複数いらっしゃいました。
良く調べ、納得し、利用するかしないかを決めましょう。
理解してやらないのと、知らずにやらないのとでは意味が違います。
これは、投資と同じですね!
メダカ家は、、、
サラリーマンにとっての数少ない節税方法であり
返礼品がもらえる楽しさもあり・・・制度にも賛同して楽しんでいます♪
限度額の目安が分かったら、様々な返礼品の中から希望の品を選んで
ふるさと納税してみましょう!
2020年のふるさと納税による寄付金控除は、12月31日までに寄付が完了したものに限ります!
せっかくの有難い制度ですので、寄付金控除の枠がある方は
是非、ふるさと納税してみて下さい♪
私のおススメ返礼品一覧
その他の個人的おススメの品をまとめています【ふるさと納税】おススメ返礼品
登録は無料、どのような返礼品があるか見るだけでも楽しいです。
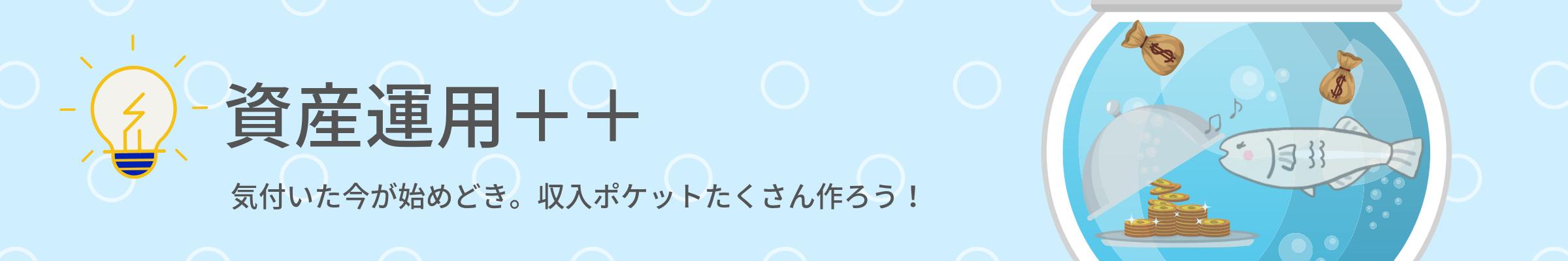
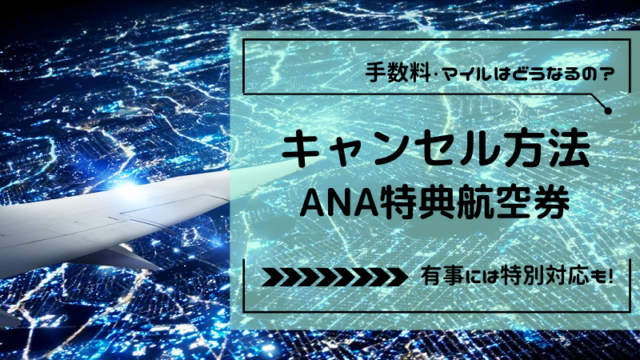

受取利息の明細公開!-1-640x360.png)



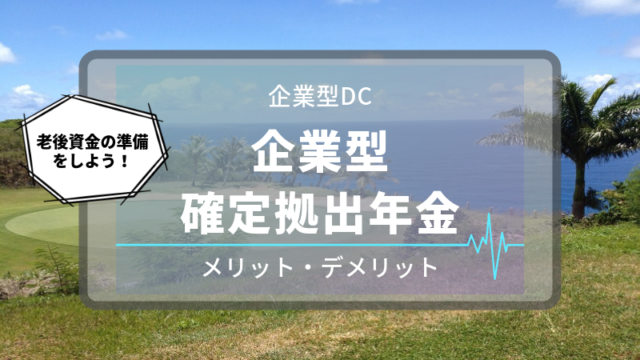

-640x360.png)